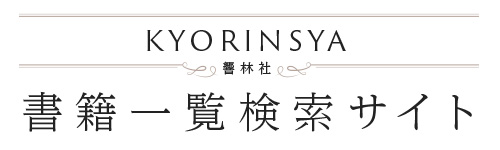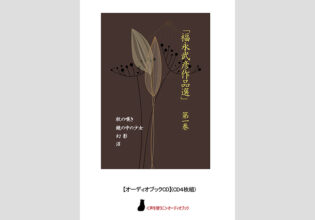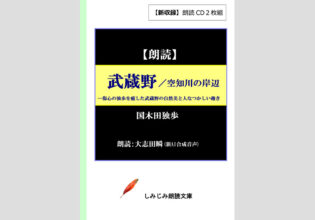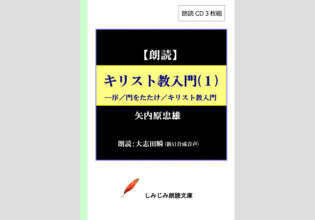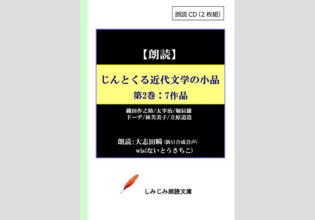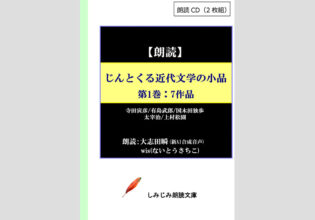【解説】
『二百十日』は、明治39年(1906年)10月に発表された。熊本での教師時代に、明治32年8月末から9月初めにかけて、同僚の山川信次郎とともに阿蘇各地をめぐり、9月1日には登頂を試みたが嵐に遭い断念しており、その体験をもとにした作品と言われている。「二百十日」とは立春から210日目の9月1日頃で、台風が来襲しやすいとの伝承がある。
圭さんと碌さんという2人の青年の軽妙な会話が中心であるが、圭さんは阿蘇山と同じく内奥にマグマがたまっていて、時世に対する悲憤慷慨を語っている。漱石が高濱虚子に宛てて書簡では、「圭さんは呑気にして頑固なるもの」「圭さんは鷹揚でしかも堅くとって自説を変じない所が面白い余裕のある逼らない慷慨家」「僕思うに圭さんは現代に必要な人間である。今の青年は皆圭さんを見習うのがよろしい」と書いている。
漱石は、明治44年の「現代日本の開化」との講演で、明治近代化を評して「我々のやっている事は内発的でない、外発的である。これを一言にして云えば現代日本の開化は皮相上滑りの開化である・・・しかしそれが悪いからお止しなさいと云うのではない。事実やむをえない、涙を呑んで上滑りに滑って行かなければならないと云うのです。」と述べているが、圭さんの人物像も、反骨精神を持ちながらも対応していくことが必要な「千変万化錯綜した」時代を背景にしたもののように感じられる。
なお、漱石はこの旅で30近い句を詠んでいる。「温泉の湧く谷の底より初嵐(戸下温泉)」、「灰に濡れて立つや薄と萩の中」、「行けど萩行けど薄の原広し」などがある。